【離婚後の共同親権とは】いつから始まる? メリット・デメリットを解説

現在の日本では、「単独親権」が採用されているため、離婚後は父親または母親のどちらかが子どもの親権者になります。
しかし令和6年(2024年)5月17日に共同親権の導入をする改正民法が成立し、令和8年(2026年)4月1日から、日本でも共同親権が導入されることが決まりました。
これまでは単独親権を前提としていたため、共同親権がどのような制度なのか、よくわからないという方も多いでしょう。共同親権導入後にしっかりと対応できるよう、制度の内容やメリット・デメリットなどを理解しておくことが大切です。
本コラムでは、離婚後の共同親権に関する概要、メリット・デメリット、親権の決め方などについて、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。
目次を
1、共同親権とは? いつからスタートするのか
最初に、共同親権の制度に関する概要と共同親権がスタートする時期について説明します。
-
(1)共同親権の概要
共同親権とは、父親と母親の双方が親権を持つ制度のことです。現在も婚姻中は共同親権ですが、改正民法の施行後は離婚後も共同親権が選択できるようになります。
親権に含まれる権限 - 財産管理権:子どもの財産を管理する権利
- 身分行為の代理権:子どもの身分行為(婚姻、離婚、養子縁組など)に同意し、代理する権利
- 居所指定権:子どもをどこに住まわせるかを決める権利
- 懲戒権:子どもを叱ったり、しつけたりする権利
- 職業許可権:子どもが職業を営む際に許可する権利
現在は、離婚後は単独親権となっているため、親権者であるどちらか一方の親のみが上記の権限を行使していました。改正民法施行後に共同親権を選択した場合には、双方の親が上記の権限を行使することができるようになります。
-
(2)共同親権はいつからスタート?
日本では、婚姻中は父親と母親の双方が子どもの親権を行使することが認められています(民法818条3項)。
離婚後については、現状は父親または母親のどちらか一方を親権者に指定しなければなりません(民法819条1項)。これを「単独親権」といいます。
しかし、令和6年5月24日、賛成多数によって共同親権を導入する民法改正案が公布されました。今後、共同親権は令和8年4月1日にスタートすることが決まっています。以下の特設ページでは共同親権の導入する背景やメリットについて詳しく解説しています。ぜひご参考ください。
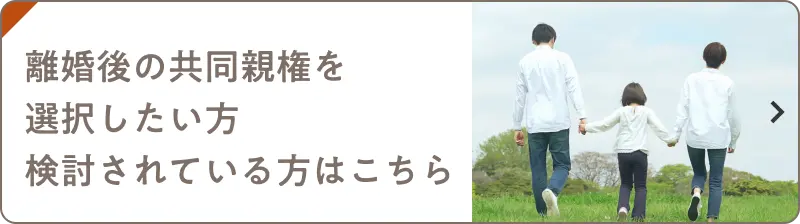
2、共同親権が導入されることになった背景
2章では、単独親権を採用していた日本が共同親権の導入決定までに至った背景を説明していきます。
-
(1)海外では共同親権が主流
法務省は、G20を含む海外24か国について離婚後の親権制度に関する調査を実施しました。その結果、離婚後の単独親権を採用している国は、トルコとインドのみで、欧米諸国、中国、韓国などほとんどの国で共同親権を採用しています。
海外では共同親権が主流であり、特に、先進国のなかでは日本だけが単独親権という状況だったため、日本でもこれに合わせて共同親権導入の議論が長らく行われてきました。 -
(2)養育費の未払い問題
離婚後のトラブルのひとつに、養育費の未払い問題があります。
単独親権によって非親権者となった親は、子どもを育てているという実感がわきにくいことが原因で養育費の滞納をしてしまっているケースも少なくありません。子どもの養育費が支払われない状況が続くと、子どもの健全な成長や発達にも重大な影響を与えてしまいます。 -
(3)離婚後の面会交流(親子交流)が行われない問題
離婚してからも、非親権者は子どもと定期的に会うこと(=面会交流あるいは親子交流)ができます。しかし実際には、親権者が面会交流を拒否するなどして、満足に子どもとの面会ができない親も少なくありません。
面会交流は、非親権者だけではなく子どもにとって重要な制度です。親権者の意向だけで子どもと親が会う機会を奪ってしまうのは問題です。 -
(4)子どもの連れ去り
国際離婚後に離婚をする際、親権の獲得を希望する日本人の親が海外から子どもを連れて日本に帰国してしまう事案があります。
このような事案に対応するため、日本では平成26年にハーグ条約を締結し、16歳未満の子どもを無断で連れ去った場合、原則として元の居住国に返還することが義務付けられました。
しかし、令和2年7月に開催された欧州議会本会議で返還執行率が低いことを指摘され、より効果的に子どもの連れ去りに対応できるよう共同親権の導入が議論されるようになりました。
3、共同親権のメリットとデメリット
共同親権には、メリットだけでなくデメリットもあると言われており、不安になる方もいらっしゃるでしょう。実際によく挙げられているメリット・デメリットを説明していきます。
-
(1)共同親権の3つのメリット
【① 離婚後も父母が協力して子育てできる】
共同親権を導入することで、離婚後も父親と母親の双方が協力し合いながら子育てに関わることが可能であると言われています。
現状の単独親権では、基本的には親権者に指定された親が子育てを担うことになります。そのため、子育ての悩みや苦労をひとりで抱えてしまい、精神的に疲弊してしまう事態も少なくありませんでした。共同親権ではそのような負担が分散するため、父母双方が平等に子どもと接する機会が増えることが期待されています。
【② 離婚時の親権に関するトラブルを回避できる】
単独親権だと、離婚時に父親または母親のどちらか一方を親権者に指定することが必要です。双方が親権を希望する場合には、離婚に合意ができていたとしても激しい親権争いが生じてしまい、離婚自体には同意があっても親権について同意できないために離婚訴訟に発展するケースも少なくありません。
共同親権が導入されることにより、親権に関する争いが減ってスムーズに離婚できるケースが増えることが期待されています。
【③ 養育費の支払いや面会交流をスムーズに実現できる】
現状は、子育てに関わることができない非親権者が疎外感を受けることから養育費の支払いを滞納することがあると指摘されています。また、面会交流を制限されてしまうことで子どもへの愛情などが薄れてしまうことが理由となって養育費の不払いが発生するケースも少なくありません。
共同親権では、父母双方が親権者として子どもにかかわっていくことができるため、定期的な面会交流が実現でき、養育費の不払いが生じるケースも少なくなると期待されています。 -
(2)共同親権の2つのデメリット
共同親権が導入されることのメリットは上記のとおりです。一方で、共同親権導入前の議論がなされている頃から指摘されているデメリットがあります。後述するデメリットについては、今後、制度の構築または運用により解消することが期待されています。
【① 子どもに掛かる負担が大きい】
共同親権となると、子どもの進学や引っ越しには双方の親権者の同意が必要となります。たとえば父母が教育方針で揉めれば、子どもは進学や引っ越しをスムーズに行うことができなかったり、板挟みになった子どもの精神的な負担が大きくなる可能性があります。
共同親権を選択した親としては子どもの利益を第一に考えて行動することが大切です。また、どのような制度・運用としていくかが今後の課題です。
【② DVやモラハラから逃げられない】
共同親権が導入されると、父親と母親の双方で子育てに関与していくため、離婚後も交流が続くことになります。離婚原因がDVやモラハラである場合にも共同親権となるとすると離婚後もDVやモラハラが続いてしまうおそれがあります。
このような事態を避けるため、改正民法では必ず共同親権とするのではなく選択制となっており、施行後も単独親権とすることが可能です。
4、単独か共同か? 親権の決め方と養育費の支払義務
4章では、共同親権導入後の親権の決め方や養育費の支払義務について、解説していきます。
-
(1)共同親権導入後の親権の決め方
共同親権が導入されると、協議離婚の際に共同親権にするか、単独親権にするかを選択することが可能です。
夫婦の協議により親権者が決まらないときは、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、そこで調停委員を介して夫婦が話し合いをしていくことになります。共同親権または単独親権のどちらにするのか、単独親権とする場合にはどちらが親権者となるのかについて合意ができれば、調停離婚が成立して親権者も定まります。
調停でも親権が決まらず、離婚も成立していないときは、最終的に家庭裁判所に訴訟を提起することが必要です。訴訟では、子どもの利益のために裁判所が一切の事情を考慮して、親権者の指定を行います。
ただし、以下のような事情がある際は、父親あるいは母親の一方を親権者に決めなければなりません。以下の事情がある場合には、裁判所は単独親権として、どちらか一方を親権者と決定します。- 父親または母親が、子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
- 父母の一方が他方からDVやモラハラを受けるおそれがあるなど、父母が共同して親権を行使することが困難であると認められるとき
このように、今後は親権の決め方で選択肢が増えることになります。
-
(2)共同親権導入後の養育費の支払義務
共同親権を選択したとしても、離婚後の養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
共同親権となった場合にも、子どもと一緒に暮らす親と離れて暮らす親がいます。現在と同様に、子どもと離れて暮らす親は養育費を支払う義務があります。
お悩みの方はご相談ください
5、弁護士からのメッセージ
共同親権導入についての改正民法が成立し、令和8年4月1日に共同親権がスタートすることが決まりました。共同親権が導入されることで、従来の親権争いが解消され、子どもをめぐる環境についても改善されることが期待されています。
もっとも、当事者としては、離婚時の親権に関する選択肢が増えることになり、どのように決めるべきかわからないことも多くあるでしょう。共同親権をはじめとした離婚に関するお悩みには、弁護士に相談することで解決が可能です。
離婚を決断している方や、すでに離婚していて面会交流あるいは養育費のことでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。離婚専門チームの弁護士が親身にお話を伺いながら、最適な解決方法をご提案いたします。
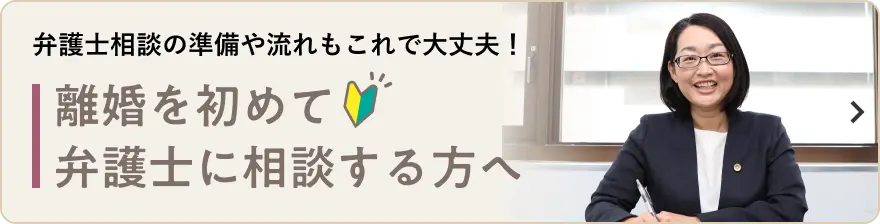
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(親権)
-
更新日:2025年11月26日 公開日:2025年08月14日
 2026年4月導入の共同親権、既に離婚している場合はどうなる? これまで単独親権が採用されていた日本でも、離婚後の共同親権を認める改正民法が令和8年(2026年)4月1日に施行されます。改正民法の施行にあたって、既に離婚している場合の親権はどうなるのだろうかと疑... 離婚・不倫コラム全文はこちら
2026年4月導入の共同親権、既に離婚している場合はどうなる? これまで単独親権が採用されていた日本でも、離婚後の共同親権を認める改正民法が令和8年(2026年)4月1日に施行されます。改正民法の施行にあたって、既に離婚している場合の親権はどうなるのだろうかと疑... 離婚・不倫コラム全文はこちら -
更新日:2022年10月11日 公開日:2022年10月11日
 家庭裁判所の「調査官調査」とは? 子連れ離婚における影響度を解説 未成年の子どもがいる夫婦が離婚をする場合には、子どもの親権者をどちらにするか決めなければなりません。夫婦間の話し合いで離婚や子どもの親権について合意ができない場合、家庭裁判所の調停や裁判手続きによる... 離婚・不倫コラム全文はこちら
家庭裁判所の「調査官調査」とは? 子連れ離婚における影響度を解説 未成年の子どもがいる夫婦が離婚をする場合には、子どもの親権者をどちらにするか決めなければなりません。夫婦間の話し合いで離婚や子どもの親権について合意ができない場合、家庭裁判所の調停や裁判手続きによる... 離婚・不倫コラム全文はこちら -
更新日:2025年05月13日 公開日:2020年12月10日
 親権争いで母親が負けるケースとは? 親権決定の判断基準も解説! 単独親権が採用されている日本では、未成熟子(経済的に自立していない子ども)のいる夫婦が離婚するとき、子どもの親権は母親が持つというケースが大半です。事実、厚生労働省が公表する「令和4年度 離婚に関す... 離婚・不倫コラム全文はこちら
親権争いで母親が負けるケースとは? 親権決定の判断基準も解説! 単独親権が採用されている日本では、未成熟子(経済的に自立していない子ども)のいる夫婦が離婚するとき、子どもの親権は母親が持つというケースが大半です。事実、厚生労働省が公表する「令和4年度 離婚に関す... 離婚・不倫コラム全文はこちら

