弁護士 安達 里美(大阪弁護士会) 弁護士 日原 聡一郎(東京弁護士会)
弁護士 安達 里美(大阪弁護士会) 弁護士 日原 聡一郎(東京弁護士会)
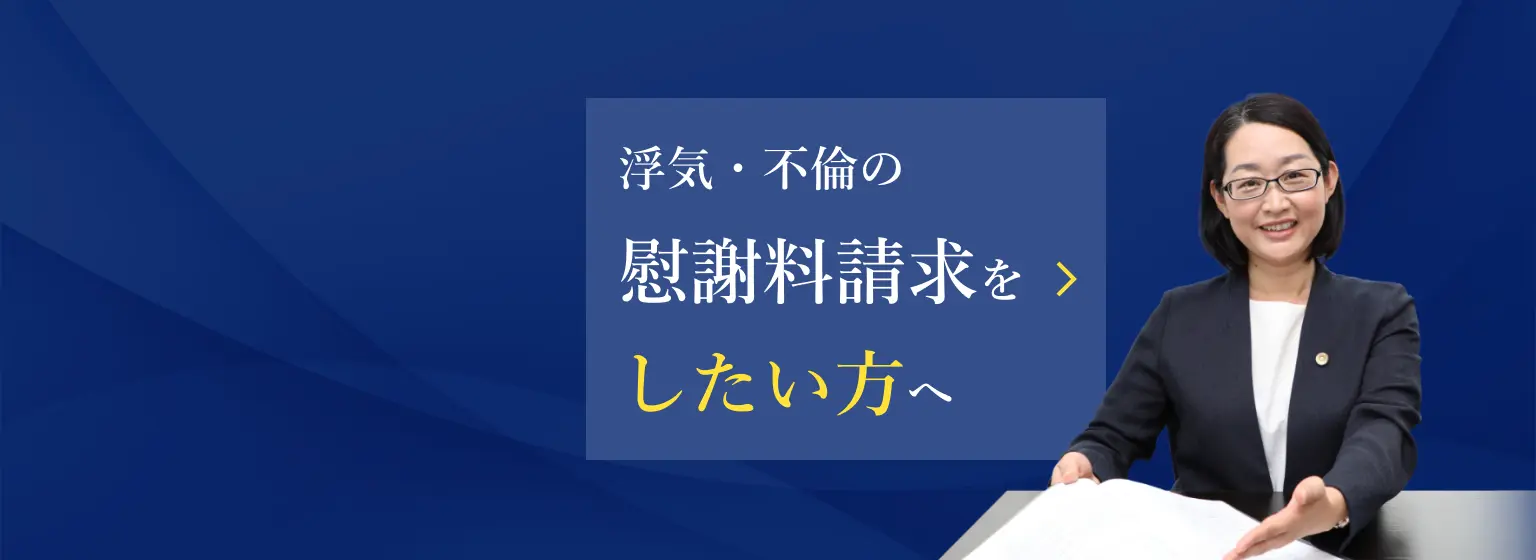
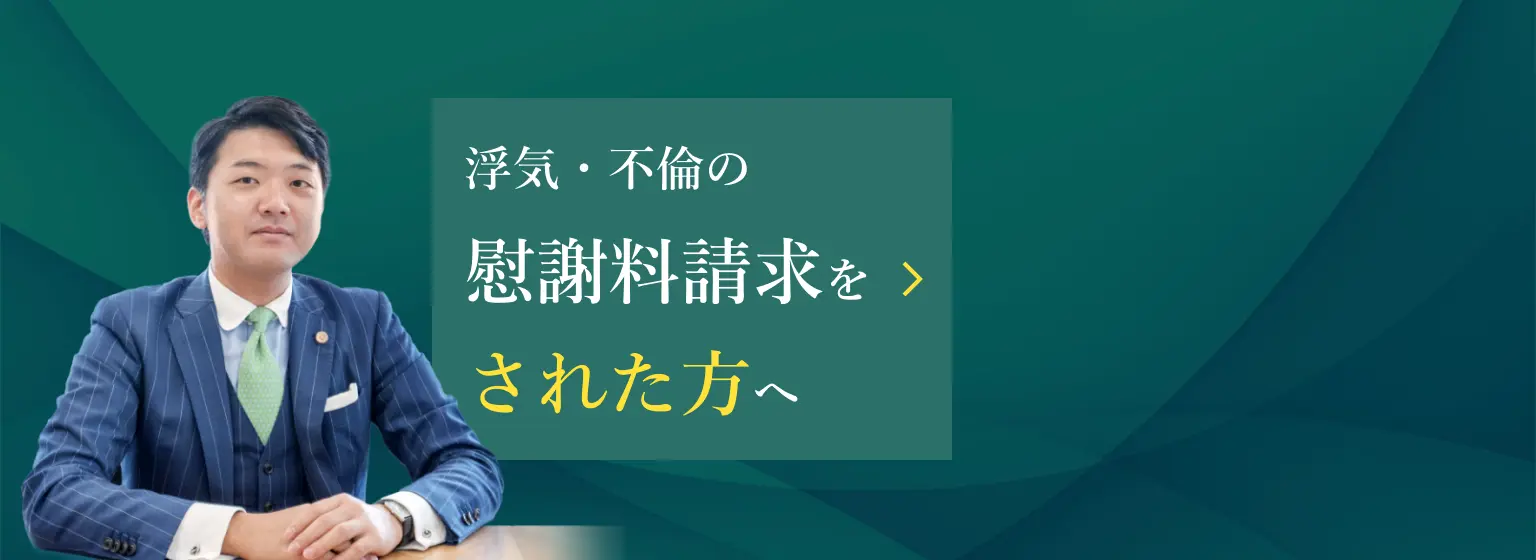

養育費や婚姻費用の金額を簡単に!
無料でチェックすることができます。
離婚のことで少しでも悩まれている方、弁護士へのご相談をおすすめします!
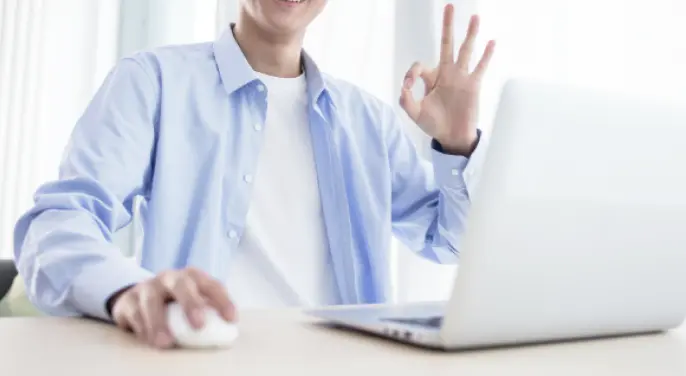
離婚したいけど、相手と話をしたくない。そんな時に、相手との離婚についての交渉を弁護士に依頼すれば、相手と直接話す必要はありませんし、第三者である弁護士を介することでスムーズな離婚も可能となります。
あなたの代わりに弁護士が相手と交渉をします。

調停にて弁護士が代わりに出頭し、有利な条件になるように話を進めます。
調停委員から難しい法律用語を言われよくわからないままに返事をしてしまうことも弁護士に依頼すればなくなります。
離婚調停や離婚裁判で有利な条件になるよう離婚成立をサポートします。

離婚に関しては、財産分与、婚姻費用、親権、監護権、養育費、慰謝料、年金分割など様々な問題があります。
離婚するときに適切な手続きを行い、離婚した後のトラブルを未然に防げます。
 浮気・不倫・セックスレス・モラハラ・DV・慰謝料請求・財産分与など…
浮気・不倫・セックスレス・モラハラ・DV・慰謝料請求・財産分与など…
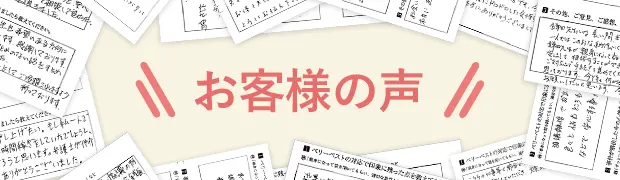 弁護士への離婚相談について全国から寄せられた
弁護士への離婚相談について全国から寄せられた
初回60分相談無料
明朗会計でリーズナブル
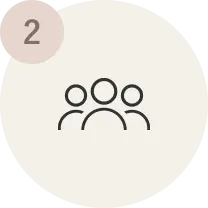
約400名の弁護士と
離婚専門チームがサポート

協議離婚から離婚後まで
サポート

ご相談に合わせて
弁護士の性別を選択できる

全国75拠点 各オフィスと
連携して遠方の裁判も対応

約140,317件の豊富な実績

お問い合わせいただいた内容をもとに、離婚専門のスタッフよりお電話もしくはメールにて折り返しご連絡をいたします。
また、対面相談・オンライン相談・電話相談とご相談形式をお選びいただけます。スタッフにご希望の相談形式をお伝えください。

ご予約が確定した日時に、お近くの事務所もしくはZoomなどにて、弁護士にお悩みをご相談ください。当日は、担当弁護士が法的観点から問題解決に向けたアドバイスや今後の見通し、費用などについて、お伝えいたします。
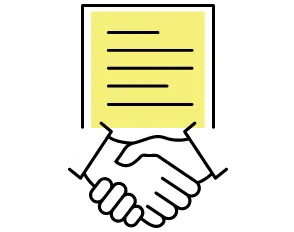
ご相談内容をもとに、弁護士から今後のプランをご提案いたします。
その内容をご確認の上で、実際にご依頼いただくかどうかをご判断ください。ご依頼を決められてから、正式に契約書を交わします。
ご相談のみでお悩みが解決した場合、費用はかかりません。
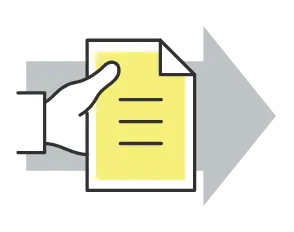
ご提案プランをもとに、担当弁護士が必要な書面の作成や、相手方との交渉などを進めていきます。
交渉により問題が解決しない場合は、お客さまに更なる方針をご相談させていただき、裁判所への調停申し立てなど、状況に応じた法的な対処を行っていきます。
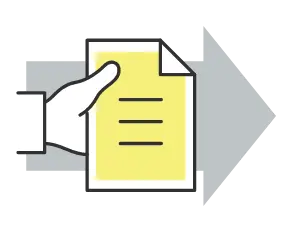

弁護士に依頼するとたくさんの費用がかかりそう…初めてご依頼いただく場合、漠然とそんなイメージをお持ちの方もいらっしゃることでしょう。
ベリーベストでは、お困りになったその時にご相談いただけるよう、初回のご相談(ご来所・オンライン)は60分まで無料となっております。
また、ご要望がございましたら、具体的なサービスを行う前に、お見積書をお渡しすることも可能です。お気軽にお申し付けください。
