卒婚とは? 離婚との違いやメリット・デメリットを弁護士が解説

夫婦仲が悪いわけでもなく、子どもや世間体のことを考えた場合に、卒婚(卒コン)を考える方もいるでしょう。
卒婚とは、離婚をせずに、戸籍上の婚姻関係を残したままで夫婦が自由な生活をおくることです。メリットだけでなくデメリットもあるため、一方的に卒婚を決めるのではなく、夫婦で話し合うことから始めましょう。
本コラムでは、卒婚の基本概要や卒婚のための4つの準備、配偶者が卒婚を拒否した場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。
目次を
1、卒婚とは?
卒婚とは、戸籍上の婚姻関係は残したまま、夫婦双方が自由に生活することです。
お互いを扶助することなく別居の形態をとったり、同居でもお互いに干渉せずに生活することを指しています。
「自由が欲しいなら離婚をすればいいのでは?」と感じるかもしれません。
しかし、子どもや世間体などを考えて、どうしても離婚はしたくないと考える夫婦には、ありがたい形になるでしょう。
2、卒婚のやりかたとは? 卒婚のための4つの準備
-
(1)家族の同意を得る
卒婚を始めたいのであれば、必ず子どもや配偶者から同意をとりましょう。一方の勝手な思いで卒婚をスタートすることは、トラブルになりかねません。
夫婦でお互いに目的を明確にし、お互いのメリットを確認してから合意してください。 -
(2)これからの夫婦の生活費を確認
卒婚したなら、お互いに自由を得る代わりに自分のことは自分でしなければいけません。
これまで通りに婚姻費用(生活費)を得られるケースは、少ないものです。自分の貯金や職業などをしっかり確保し、卒婚後もゆとりある生活ができるように準備を進めてください。
家庭内卒婚のケースでは、家事をこれまで通りにする代わりに、その報酬を配偶者から得る方法もあります。また、夫側から卒婚を望んでいるケースでは、これまで通りに婚姻費用をもらえる可能性が高いといえます。
卒婚をするのであれば、トラブルを回避するためにも、卒婚後の生活費のことはしっかり双方で確認するようにしてください。 -
(3)新居を探す
別居卒婚なら、卒婚するまでには新居を探しておいた方がスムーズです。
新居と共に、生活に必要な家具・家電製品なども取り揃えておけるとよいでしょう。
卒婚は婚姻関係がそのまま続くことになるため、卒婚後に夫婦で会う頻度などを決めて、その頻度に合わせた距離感の場所に新居を探すようにしてください。
今後一切理由がない限りは関わらないなどと決めているなら、遠くに引っ越しても問題ないかもしれません。ですが、子どもを介して月に一回は会う可能性がある場合、比較的に近い距離に住んでいたほうが好都合です。 -
(4)お互いが病気になった場合、介護が必要になった場合にどうするのかの取り決め
卒婚は離婚とは異なり、相続関係も継続するものです。
お互いに自由を満喫できる間は卒婚で満足できますが、病気や怪我などがあった場合には満足できないケースもあるでしょう。
そういった事情が生じることに備えて、「元の結婚生活に戻るのか」「それともお互いに他人として生きていくのか」ということを取り決めておければ安心です。
卒婚はあくまでも離婚とは違うことを認識し、お互いに介護が必要になった場合なども想定して卒婚をそれでも継続するのか夫婦間で話し合っておきましょう。
3、離婚や別居との違いとは?
-
(1)卒婚と離婚の違い
卒婚と離婚で変わること・変わらないことについて、以下で6つご紹介します。
【① 入籍したまま】
卒婚は婚姻関係が継続するものですが、離婚は婚姻関係が終わりになるものです。
つまり、婚姻関係は継続したまま、自由だけを手に入れる手段と考えてください。もちろん面倒な手続きも必要ありません。
離婚手続きをしないので、夫との話し合いでいつでも卒婚を解消して元の結婚生活に戻れることもポイントです。「少しだけ自由を手に入れたい」という場合には、数年間限定で卒婚してみるのも良いでしょう。
【② 家族でありながらもお互いに細かな点を干渉しない】
婚姻関係は継続するわけですから、卒婚しても家族であることには変わりはありません。
家族とのイベントは今まで通り楽しむことができまずが、卒婚したことで互いに細かな点で干渉することができなくなります。
たとえば、干渉されずにいつまでも好きなだけダラダラできますし、お酒を好きなだけ飲むこともできるでしょう。夜に友人と食事に出ても、配偶者から干渉されることはなくなります。数日間洗濯物を溜め込んだとしても、それは本人の自由なのです。
【③ 相続関係がそのまま】
卒婚では、法定相続関係が変わることはありません。 離婚をすれば、長年夫婦として歩んできて支えとなってきた配偶者であっても、財産の相続することができなくなってしまいます。
卒婚ならば、長年支えた配偶者の財産は正当に相続することが可能です。
【④ 居住スタイルを選択できる】
離婚とは違い、同居するのも別居するのも自由です。
お互いに同意ができたなら、婚姻関係はそのままに別居できる特徴もあります。
「同居のまま離婚」は世間体もあって難しいこともありますが、当事者の意思のみで成り立っている卒婚ならば、相談次第で住居スタイルは自由に選択することが可能です。
以下、卒婚の3つのスタイルを見ていきましょう。・家庭内卒婚
いきなり別居をする経済的な自信がない方は、家庭内卒婚を選ぶと良いでしょう。同居しながらもお互いに干渉せずに自由を満喫するスタイルです。
話し合いで家事の一切を別にすることもできますし、家事はするけどその報酬を配偶者から受け取るというようなこともできます。
・週末卒婚
週末だけ卒婚するスタイルを選ぶ夫婦もいます。
いきなり別居をして新居を構えることが難しい場合には、週末だけ一方がホテル住まいするなどの方法です。気分もリフレッシュできますし、平日は普段通りの結婚生活を送るスタイルとなります。
週末だけは自由を手に入れられることができるので、なんだかんだ言って夫や妻を放ってはおけないタイプや、少しだけ自由を手に入れたいタイプの方には適したスタイルになるでしょう。
・別居卒婚
完全に生活を別にしたい場合には、別居卒婚がおすすめです。本心では「離婚をしたい」「住環境を今まで相手に合わせてきた」などのケースでは、別居卒婚をすべきといえます。
完全に別居するわけですから、夫と顔をあわせる機会も少なく、それでも結婚している世間体は保つことが可能です。
【⑤ お互いに世間体を保てる】
離婚と違い、卒婚では、「お互いに配偶者がいる」という世間体を保てるのがポイントです。
たとえば、会社の部下の結婚式や親族の集まりの際にはお互いに合意し一緒に参加することができます。「最近、旦那さんはどうしたの?」などの問いに対しても、「仕事が忙しいみたい」などと配偶者の近況に答えることもできるでしょう。
各書類の「配偶者」の欄も、空欄にする必要はありません。
【⑥ 子どもや親を傷つけない】
何よりも離婚と違う卒婚のメリットは、子どもや親を傷つけないことではないでしょうか。
いくつになっても、両親の離婚は子どもの心を傷つけます。また、熟年離婚をしては、年老いた両親が心配するケースもあるでしょう。 -
(2)卒婚と別居の違い
離婚届を提出せず、婚姻関係を継続するという点では共通します。
しかし卒婚の場合は、一緒に暮らしているか、別々に暮らしているかは関係ありません。
別居は、婚姻関係を継続しながらも必ず夫婦が別々に暮らすという点で、卒婚とは異なります。
4、あなたも当てはまる? 「卒婚したい」と考える5つの理由
どういう理由から「卒婚」という形を取り入れたいのか、他の人の考えが気になるという方もいるでしょう。4章では、卒婚を考え得る理由について、5つ紹介していきます。
-
(1)夫の世話から解放されたいから
子どもが巣立った場合や夫の定年退職を契機に、「どうせなら夫の世話から解放されたい」と感じる女性は少なくありません。
夫が朝から晩まで家にいる場合には、会社勤めのときとは変わり、一日中世話を焼かなければいけない家庭もあるはずです。そうすると、自由に出歩くことも制約される可能性があります。
「夫の世話の一切から解放されたい」という思いから、卒婚を考える人も多いでしょう。 -
(2)友人などと自由に旅行を楽しみたいから
結婚生活では、配偶者から自由に出歩くことも制約を受けてしまいます。友人と旅行に行くのにも、妻や夫の許可が必要というケースもあるでしょう。
卒婚すれば、自分だけの都合で自由に出歩くことができます。家族から解放されたときに最初にやりたいことは、自由に出歩くことではないでしょうか。 -
(3)趣味や仕事に時間を忘れて没頭したいから
趣味や仕事に没頭したいがために、卒婚を考える方も少なくありません。
「時間を気にせず好きなことがしたい」という思いがあって卒婚を始めた方は、自由を満喫できる解放感に気持ちが満たされることでしょう。
-
(4)自由になりたいから
当然、卒婚をしたい大きな理由は「広義の意味での自由の入手」です。
誰にも口出しされずに自分だけの時間を手に入れるためには、家族の世話があってはできるものではありません。1人だけの時間を手に入れられる点で、卒婚を選択する人がいます。 -
(5)ずっと我慢してきたから
卒婚をしなければ、「自分の自由」を叶えられないのは、これまで配偶者があなたに対して圧を加え続けていたからかもしれません。
家族のことを思って、自分の望む生活や時間を犠牲にしてきた方も少なくないでしょう。
それは、激務な仕事でも耐え忍んだ日々だったり、ワンオペで孤独な中での家事・育児だったり、人によってさまざまです。
このように、積み重なった「我慢」が限界に達したとき、卒婚あるいは離婚という選択を考える方もいます。
5、卒婚に隠された4つのリスク
-
(1)離婚と違って再婚はできない
戸籍上は夫婦となっているため、卒婚を選んだ場合に再婚はできません。
配偶者以外に他に好きな人ができて、再婚目的に卒婚するのなら間違いです。正式に離婚してからでないと、結婚できないことにご注意ください。 -
(2)恋人ができたら不貞行為となり得る
万が一、卒婚で自由を手にして好きな異性ができたとしても、恋人としてお付き合いをするのは要注意です。離婚していない限りは、不貞行為になり得ます。
もしも配偶者に事実が知られた場合には、慰謝料請求の対象になる可能性があるだけでなく、最悪のケースでは離婚に発展してしまいます。
そうならないためには、「卒婚後、恋愛は自由にできる」などの取り決めをしておき、書面に残すようにしましょう。 -
(3)十分な生活費がないと難しい
卒婚で自由を手に入れたい場合には、十分な生活費が必要になります。
別居卒婚ならば、当然に家賃や光熱費、通信費など多額のお金がかかります。週末卒婚でも、週末の宿泊費用や自由に出歩くお金は必要です。
家庭内卒婚であれ、家事の一切を放棄するなら、それなりのお金は必要になると考えておくとよいでしょう。 -
(4)離婚につながる危険性がある
卒婚から離婚につながるリスクは、どうしても高くなります。
長期間の別居を行えば互いの愛は冷めてしまい、「卒婚している配偶者に遺産を残す必要があるのか?」と疑問を感じ始めることもあるでしょう。
卒婚は、初めのうちは自由を満喫できることにお互い喜びを感じるかもしれません。しかし、長引くほどに他に好きな人ができたり、「どうせなら離婚した方が一切のしがらみがなくなり良いのでは?」と感じることもあります。
そもそも、長期間の別居は夫婦関係の破綻を意味するとされています。
きちんと、単なる別居ではなく「卒婚」なのだということを書面などに記しておかなければ、配偶者が離婚裁判を起こせば、離婚につながる危険性は高くなるといえるでしょう。
6、卒婚に前向きになっても良い家庭の特徴3つ
-
(1)妻が職に就いているか預貯金が多い
卒婚するためには、ある程度のお金が必要です。
これまで妻が夫に扶養してもらっていたのなら、貯金を貯めておくか、職業についているほうが無難でしょう。
法律上、配偶者への婚姻費用の請求は可能ですが、相手が支払いに合意しない場合、「裁判してまで獲得する」というのは、望むところではないはずです。
仮に収入が少ない、もしくは無収入の場合は、卒婚を切り出す前に収入を増やすことを検討しましょう。 -
(2)子どもや配偶者が自立した生活をしている
まだ子育てが終わっていない段階での卒婚は、おすすめできません。
子どもと一緒に家を出たとしても、今まで健康だったはずの子どもの急な病気、学校でのトラブルなど、子どもの世話が一気に押し寄せてきてしまいます。そのため、子どもが独り立ちしているほうが卒婚を満喫できるでしょう。
また、配偶者も自立した生活ができなければ、そもそも卒婚を受け入れてもらえない可能性が高いといえます。 -
(3)配偶者に趣味などがあり、自由を欲しがっている
また、卒婚は夫婦共に自由を満喫することが目的です。
ですから、双方が自由を欲しがっている夫婦こそ、卒婚が向いている家庭といえるでしょう。夫や妻に趣味があり、時間を気にせずに没頭したがっているなら、卒婚を受け入れてもらえる可能性があります。
7、卒婚に同意してもらえないときの対処法
-
(1)申し入れがあったときに卒婚を解消し、夫婦関係に戻れる条件をつける
夫や妻から卒婚に同意してもらえない場合は、「申し入れがあれば、いつでも卒婚を解消でき、夫婦関係に戻れる」と書面に残してみてください。
最初は卒婚に不安を感じていた配偶者も、安心できる可能性があります。
卒婚を満喫し、羽を伸ばして過ごすうちに、卒婚の良さを理解してもらえる可能性もあるでしょう。
ただし、約束に従い、夫や妻からの申し入れがあれば夫婦に戻る必要があります。 -
(2)自分で生活費が工面できる場合は「生活費はいらない」と宣言する
婚姻関係は続いているわけですから、卒婚でも婚姻費用は請求することができます。
ですが、配偶者がどうしても卒婚に同意しない場合には、「生活費は必要ありません」と宣言してみてください。お金が要らないなら、「自由をあげよう」と納得してくれるはずです。 -
(3)「恋人は自由に作っても良い」と取り決める
「卒婚するなら、お互いに恋人は自由に作っても良い」と明言すれば、卒婚を受け入れてもらえる可能性があります。これまで浮気癖がある配偶者だったのなら、受け入れられやすい条件になるでしょう。
-
(4)弁護士に相談する
弁護士は、あなたの気持ちを受け止めながら、法的にどのようなサポートができるかを検討します。夫や妻に卒婚を提案した際に説得しきれず、トラブルが生じたときは、どのように話を進めていくべきかをアドバイスしたり、間に入って話し合いを調整したりすることも可能です。
卒婚ではなく離婚となった場合でも、財産分与や養育費の取り決めについて、後悔がないようにサポートいたします。
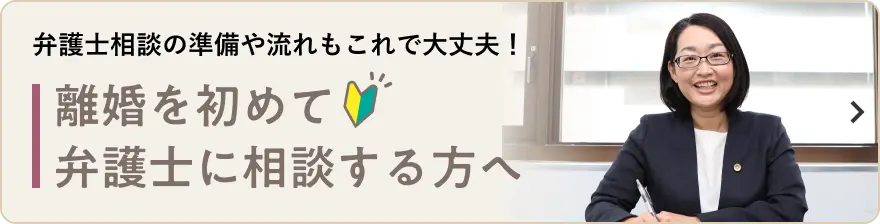
8、弁護士からのメッセージ
卒婚は、子どもや世間体を考える人にとって、「夫婦」の形と同時に自由を手に入れることができる方法です。
卒婚を始めてみてから、離婚を選択することもできますし、「やはり配偶者である夫(妻)を愛している」「放っておけない」と感じたなら、いつでも結婚生活に戻れるというメリットもあります。一方で、不貞行為や生活費の問題などのデメリットもあることに注意しましょう。
もし、卒婚ではなく離婚を選ぶことになった場合は、財産分与や養育費の取り決めがあるため、弁護士に相談することがおすすめです。弁護士は、後悔のない離婚が実現できるように、精一杯サポートいたします。
ベリーベスト法律事務所では、離婚専門チームを編成しており、離婚問題の経験・知見豊富な弁護士が親身になって対応いたします。
なお、弁護士相談の方法としては、お近くの事務所での対面だけでなく、Zoomを活用したオンライン上で行うことが可能です。まずは当事務所までご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(離婚)
-
更新日:2026年02月04日 公開日:2026年02月04日
 デキ婚の離婚率とは? 高いと言われる理由や婚約破棄の注意点 「授かり婚」や「できちゃった婚」とも呼ばれるデキ婚は、子宝に恵まれて幸せなスタートを切る一方で、「離婚率が高い」と言われることもあります。厚生労働省の人口動態統計を見ても、結婚したカップルの約3組に... 離婚・不倫コラム全文はこちら
デキ婚の離婚率とは? 高いと言われる理由や婚約破棄の注意点 「授かり婚」や「できちゃった婚」とも呼ばれるデキ婚は、子宝に恵まれて幸せなスタートを切る一方で、「離婚率が高い」と言われることもあります。厚生労働省の人口動態統計を見ても、結婚したカップルの約3組に... 離婚・不倫コラム全文はこちら -
更新日:2026年02月04日 公開日:2026年02月04日
 配偶者のいびきでストレスや健康被害が……離婚できる? 弁護士が解説 夫や妻のいびきが原因で眠れない、夜中に何度も目が覚めるといった悩みを抱えている方は少なくありません。慢性的な睡眠不足は、心身に大きなストレスをもたらし、仕事や家庭生活に支障をきたすこともあります。な... 離婚・不倫コラム全文はこちら
配偶者のいびきでストレスや健康被害が……離婚できる? 弁護士が解説 夫や妻のいびきが原因で眠れない、夜中に何度も目が覚めるといった悩みを抱えている方は少なくありません。慢性的な睡眠不足は、心身に大きなストレスをもたらし、仕事や家庭生活に支障をきたすこともあります。な... 離婚・不倫コラム全文はこちら -
更新日:2025年12月24日 公開日:2025年12月24日
 子持ち男性が離婚を決めるときとは? 知っておきたい兆候と対策 夫との夫婦関係が悪かったり、夫の態度や行動に違和感を覚えるような変化があったりすると、「もしかして離婚を考えているのでは?」と思ってしまうこともあるでしょう。実際、子どもがいる家庭で急に夫から「離婚... 離婚・不倫コラム全文はこちら
子持ち男性が離婚を決めるときとは? 知っておきたい兆候と対策 夫との夫婦関係が悪かったり、夫の態度や行動に違和感を覚えるような変化があったりすると、「もしかして離婚を考えているのでは?」と思ってしまうこともあるでしょう。実際、子どもがいる家庭で急に夫から「離婚... 離婚・不倫コラム全文はこちら

