熟年離婚には事前準備が必須! 後悔しないために知っておくべきこと

仕事や介護、子どもの成長をきっかけに、長年連れ添った配偶者との熟年離婚を選択する方は少なくありません。
しかし熟年離婚だからこそ、年金分割や財産分与のことなど、しっかりと押さえておくべきポイントがあります。離婚してから後悔することがないように、事前に準備しておきましょう。
本コラムでは、熟年離婚を成功させるために備えるべきことや注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 離婚・男女問題専門チームの弁護士が解説します。
1、熟年離婚とは? データで見る熟年離婚率
「熟年離婚」とは、どのような夫婦の離婚を言うのでしょうか。
言葉から考えますと、ご高齢の夫婦が離婚するケースのことを表しているようにも見えますが、熟年離婚とは、一般的には婚姻期間が20年以上の夫婦が離婚する場合を言います。
そして、熟年離婚件数はここ最近増えています。
厚生労働省が発表する「令和4年度 離婚に関する統計の概況」によると、離婚した夫婦のうち同居期間が20年以上の割合(すなわち、熟年離婚の場合)は、平成11年までは上昇傾向にあり、その後若干の増減を繰り返し、令和2年には21.5%となっています。
前回調査が行われた平成20年の時点では16.5%だっため、熟年離婚率が上がっていることがわかります。
2、熟年離婚の原因・理由で多いものは?
-
(1)夫が定年退職したこと
夫が定年退職を迎え、特に趣味等が無い場合には、家にいる時間が必然的に増えます。
そうすると、今までいなかった夫が家にいることで、今までは感じなかったストレスなどから解放されたいと考えて、離婚したいと思うようになるのです。 -
(2)夫が家事を手伝わない
今までは夫は外で仕事、妻は家の中で家事をしていたわけですが、夫の定年退職後は夫も家にいる時間が増えるわけですから、妻としては夫にも家事を手伝ってほしいと考えることがあります。
しかし、ずっと家にいるにもかかわらず夫は家事を全く手伝ってくれないことも少なくありません。そうすると、妻の不満が溜まって、離婚に踏み切るようなこともあり得ます。特に、友人・知人の旦那さんが家事を手伝ってくれているような場合には、より一層自分の夫への不満が高まり、離婚の引き金になりかねません。
他方で、夫が家事を手伝ってくれるようになったものの、今まで家事などやったことがないために、かえって時間がかかったりすることに不満を覚え、離婚を決意する人もいるようです。 -
(3)夫の年金をもらえるようになった
近年の法改正によって、夫が納めていた厚生年金・共済年金の一部を妻が年金分割制度を利用することでもらえるようになりました。
この年金分割制度によって、夫の年金の一部をもらえることができるようになった結果として、老後の生活が一定程度ではありますが、保障されるようになりました。 -
(4)夫(または妻)の親の介護をしたくない
結婚生活が20年以上になる夫婦の場合、その夫婦の親御さんがご健全な場合には、それ相応の年齢に達していることが予想されます。そのため、介護の問題がでてきます。
正直、自分の実親の介護ですら大変なのにもかかわらず、介護するのが義理の親になればその苦労は想像に難くありません。
特に、結婚生活が20年以上の夫婦の場合ですと、一般的に、夫の親の介護は嫁がするものという考え方が定着しており、妻が大変な苦労をして夫の親を介護しても、そのことに対して夫が感謝の気持ちすら示さないということもあります。
そうなってしまう結果として、そのような夫の態度に妻が嫌気をさして離婚するということもあり得ます。そして、このような場合の離婚は、特に、「介護離婚」と言われることがあります。 -
(5)夫(または妻)に好きな人ができた
夫(または妻)に好きな人ができたため、離婚するケースもあります。
最近では、ご高齢の方が集うイベントやご高齢の方でもインターネットを使える方が増えてきていることから、出会いのきっかけも多くなっている傾向です。
今の夫(または妻)よりも好きな相手ができ、その人と残りの人生を過ごしたいと思うこともあり得ます。
そうした事情もあるので、夫(または妻)に他に好きな人ができたことで熟年離婚することもあります。 -
(6)夫のDVやモラハラに耐えられなくなった
少しくらいのDVやモラハラならば耐えられた場合でも、夫が定年退職することで夫と家にいる時間が増えることで、DVやモラハラにこれ以上は耐えられないと考え、熟年離婚に踏み切る方もいらっしゃいます。
お悩みの方はご相談ください
3、熟年離婚を成功させるために絶対おさえておきたいポイント
-
(1)年金分割
まず、熟年離婚を後押ししている要因と言われている年金分割が熟年離婚を成功させるための一つのポイントです。
年金分割制度とは、夫婦各自が支払った年金保険料を決められた割合で分ける制度のことを言います。
従前、専業主婦が離婚したケースにおいて、もらえる年金の額が少なすぎるという問題がありました。そこで、この問題に対処するために法改正を行ったことで、離婚後に妻が夫の年金の一部をもらえることができるようになりました。
具体的には、専業主婦の場合には夫が納めていた年金保険料の一部を妻が支払っていたものとして扱い、将来受け取ることのできる年金額を計算するようにしました。
以下で、簡単にではありますが、年金分割制度について説明します。離婚後の生活をきちんと送れるようにするためにも、年金分割はきちんと行うようにしましょう。
①年金分割の種類は2つ
- 合意分割制度…夫婦間の合意または裁判所の決定による厚生年金・共済年金の分割制度
- 3号分割制度…第3号被保険者が請求した場合に分割対象の年金を2分の1に分割する制度
②分割の対象
- 合意分割制度…婚姻期間に夫婦双方が支払った厚生年金・共済年金保険料の納付記録を合算したもの
- 3号分割制度…平成20年4月以降に相手が支払った厚生年金保険料の納付記録
③分割の割合
- 合意分割制度…0から2分1
- 3号分割制度…例外なく2分の1
④分割の期限
- 合意分割制度・3号分割制度ともに、離婚後2年以内に請求する必要がありますので、後回しにせずできるだけ早く手続きをするようにしましょう。
-
(2)財産分与
また、夫婦が結婚してから築いた財産は夫婦の共同財産として、財産分与の対象になります。
なお、夫婦が結婚前から持っていた財産や相続などによって受け継いだ財産(=特有財産)は、財産分与の対象外であることにご注意ください。
①具体的な方法
- 現物分割…財産を夫婦のうちどちらが取得するのかを決める方法
たとえば、車は夫、家財道具一式は妻といったような決め方です。 - 換価分割…財産を売ってお金にした上で、そのお金を夫婦で分ける方法
現物分割ができないような場合や夫婦双方がその財産自体を欲しくない場合にこの方法を用います。
②分割割合
財産分与の割合は、夫婦の働き方(夫婦共働きなのか、それとも夫婦のうち片方のみが働いているのか)によって若干の違いはありますが、基本的には2分の1です。
③財産分与の対象
財産分与の対象は婚姻期間中に共同して築いた財産の一切です。ただし、マイナスの財産(住宅ローン等)も考慮するので、トータルするとマイナスになるという場合には財産分与が行われないということになりますので注意が必要です。
具体的には、以下のようなものが財産分与の対象になります。- 現金
- 不動産(土地・建物)
- 有価証券(株券・社債など)
- 家財道具(家具・家電など)
- 厚生年金・共済年金
- 退職金
など
④財産分与の期間制限
離婚後2年以内に請求する必要がありますので、とりあえず財産分与はいいやなどとは思わず、できるだけ早く財産分与するようにしましょう。
- 現物分割…財産を夫婦のうちどちらが取得するのかを決める方法
-
(3)友人や知人を作っておく
熟年離婚をすると、孤独感を感じることが多いと思います。
そこで、熟年離婚をして孤独感を感じないようにするためにも、友人や知人をきちんと作っておき、その方々と交流する機会を増やして、自分が熟年離婚をしても自分の居場所があるようにしておくと良いでしょう。
そうすれば、もし熟年離婚をして長年連れ添った夫(または妻)と別れて別々な生活を送っても、感じる孤独感は少なくなるでしょう。
「離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください」のページでは、財産分与の対象になるもの・ならないもの、注意点などについて解説しています。ぜひご参考ください。
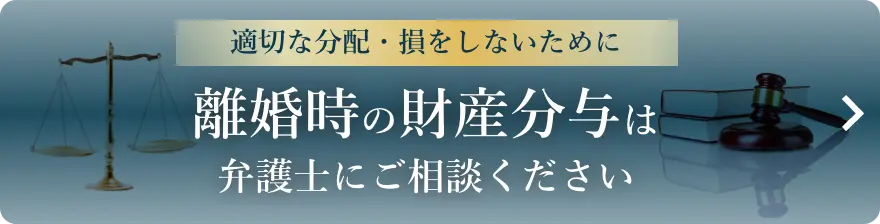
4、熟年離婚の準備としてやっておくべきこと
-
(1)お金の面
離婚するにあたって、まず心配になることがお金の問題でしょう。
特に結婚後、ずっと専業主婦をしていた方の場合には、離婚後、今度は自分で収入を得なくてはならなくなるため、そのことで離婚を躊躇してしまう方も中にはいらっしゃるかもしれません。
そのため、離婚後にご自身だけで生活していけるように、まずはご自身が1か月あたり、どの程度の収入があれば最低限生活できるのかを確認してみると良いでしょう。
もし、専業主婦の方で家計簿をつける習慣がある方であれば、生活にどれくらいのお金が必要になるかがお分かりでしょう。
また、離婚に際してもらえるお金についても知っておくことも重要でしょう。この点については、次の章で説明しています。 -
(2)住まいの面
離婚する場合には、夫婦のどちらかが今の家から出て行く必要があります。もし、あなたが今の家から出ていくことになるのであれば、新たな住まいを探す必要が出てきます。
新たに住まいを借りることになる場合には、賃料の支払いが滞るのを防ぐために、保証人をつけることを要求されるケースが多いため、保証人を見つけなければなりません。
もちろん最近では、保証人の代わりに保証会社を充てる場合もありますが、借りようとしている物件が必ずしも保証会社でも可能な物件とは限らないでしょう。
そのため、ある程度の年齢にいってから新たに住まいを確保するのは難しい場合もあります。
もし、ご実家があるのであれば、実家で新たな生活を送るというのも一つの手ではあります。 -
(3)精神的な面
前述しましたが、熟年離婚をすると孤独感を感じることが多いと思います。
そこで、熟年離婚をして孤独感を感じないようにするためにも、友人や知人をきちんと作っておき、その方々と交流する機会を増やして、熟年離婚をしても自分の居場所があるようにしておくと良いでしょう。
お悩みの方はご相談ください
5、熟年離婚する際にきちんと決めておくべき4つのこと
-
(1)慰謝料
まず、慰謝料の問題については熟年離婚する際にきちんと決めておくべき事柄です。
慰謝料は離婚原因によってもらえる金額に違いがあります。おおよその相場としては、以下の通りです。- 不倫・浮気が離婚原因の場合…100万円から500万円
- DVやモラハラが離婚原因の場合…50万円から300万円
- 悪意の遺棄が離婚原因の場合…50万円から300万円
-
(2)財産分与
財産分与については先程ご説明した通りです。
-
(3)親権
もし、夫婦の間に成人に達していない子供がいる場合には、親権者を夫婦のいずれかに定める必要があります。また、親権者にならなかった者との関係では面会交流について決める必要が出てきます。
-
(4)年金分割
先程ご説明したように、合意分割・3号分割の方法によって夫が納めていた年金を妻も一定の割合でもらえることができるようになりました。
合意分割制度の場合には、婚姻期間に夫婦双方が支払った厚生年金・共済年金保険料の納付記録を合算したものを0から2分1で分けることになります。
これに対して、3号分割制度の場合には、平成20年4月以降に夫婦の一方が納めた厚生年金保険料の納付記録のうち2分1をもらうことが可能です。
「離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください」のページでは、財産分与の対象になるもの・ならないもの、注意点などについて解説しています。ぜひご参考ください。
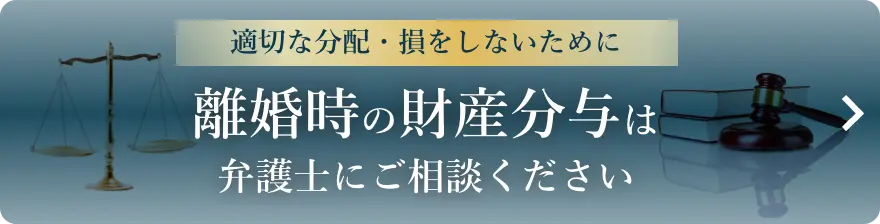
6、熟年離婚を話し合いで有利にまとめる方法
-
(1)相手を尊重する
協議離婚の話し合いにあたっては、まずは感情的にはならないようにし、できるだけ相手を尊重するようにしましょう。
長年連れ添った夫婦の一方から離婚の話が出た場合には、相手は驚いたり、場合によっては怒りの念に駆られることもあると思います。そのような場合に、相手と同じように、感情的に話し合ってしまえば、離婚の話は一向に進まないことになってしまいます。
また、感情的に話し合いを進めてしまった結果、本来話し合いがまとまるようなケースであった場合でも話がまとまらないという事態も起こり得ます。
そのため、協議離婚の話し合いを進める際には、できるだけ冷静に話し合い、相手を尊重することを心掛けると良いでしょう。 -
(2)話し合いを弁護士に代わってもらう
なかには、もはや長年連れ添った相手と話もしたくないという方もいらっしゃるかもしれません。
はたまた、話し合う内容が法律の内容であることから、全く何から話をしていいか分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
そのようなときには、話し合いを弁護士に代わりに行ってもらうことで、離婚条件の話し合いを有利に進めてもらうことが期待できます。
弁護士は法律の専門家でありますが、それと同時に交渉術を兼ね備えているため、こちらに有利な離婚条件を引き出すことが可能です。
お悩みの方はご相談ください
7、熟年離婚のケースで有利に調停を進める方法
-
(1)調停委員を味方につける
離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って、離婚の話し合いを進めます。
調停委員は、あくまで公正な立場から、話し合いの交通整理をするわけですが、離婚調停において調停委員は重要なポジションにいます。調停の場でこちらの主張を認めてもらうようにするためには、調停委員を味方につけることが大切です。
調停委員を味方につけるためには、少し語弊があるような言い方になってしまいますが、調停委員に「同情」してもらうことが必要になります。そのためには、当事者の印象が重要となってくるため、相手の悪口を言ったりするようなことは控えるようにしましょう。 -
(2)離婚調停申立書の記載内容に十分配慮する
離婚調停を申し立てるには、離婚調停申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。
そして、調停委員は、提出された申立書を事前に読んで状況を把握しますので、申立書に記載されている内容が、調停委員の印象付けることになります。
もし、結婚期間中にあなたがつらい思いをしていたのであれば、その事実を具体的に記載すると良いでしょう。
ただし、申立書にはあまり相手の悪口を記載するようにしないことを心掛けましょう。一般的にではありますが、悪口を多く言う人はあまり良い印象を持たれないためです。 -
(3)弁護士に依頼する
離婚調停をしようとした場合、必ず弁護士に依頼する必要はなく、もちろん、本人のみで離婚調停を行うことは可能です。
しかし、弁護士に依頼したという事実は調停委員に、「この人は本当に離婚したいんだろう」という印象を与えることが可能になります。なぜなら、本来弁護士を使わなくてもいい調停に、弁護士費用を支払ってまで弁護士を付けてきたということで、その人の離婚に対する本気度をアピールすることが可能になるためです。
そのため、場合によっては弁護士に依頼することも視野に入れてみると良いでしょう。
8、弁護士からのメッセージ
平成20年以降、あらゆる原因・理由から熟年離婚を選択する方が増えてきているのが実情です。熟年離婚だからこそ、年金分割や財産分与の問題など、知っておくべきと言える事柄も多くあります。
後悔のない離婚を成立させるためにも、不安がある際には弁護士に相談することがおすすめです。
熟年離婚をお考えの方は、ぜひベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。適切な離婚条件の取り決めなどを実現するべく、離婚専門チームの弁護士が真摯に対応いたします。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(熟年離婚)
-
更新日:2025年03月26日 公開日:2025年03月26日
 50代で離婚するメリット・デメリットは? 財産分与や年金分割を解説 50代は、子どもが独立し、お金にも時間にも余裕が出てくる年代といえます。一方で残りの人生を意識し、離婚を決断する方がいるのもこの年代です。50代で離婚をするには、その後の生活費や住まいの確保などをし... 離婚・不倫コラム全文はこちら
50代で離婚するメリット・デメリットは? 財産分与や年金分割を解説 50代は、子どもが独立し、お金にも時間にも余裕が出てくる年代といえます。一方で残りの人生を意識し、離婚を決断する方がいるのもこの年代です。50代で離婚をするには、その後の生活費や住まいの確保などをし... 離婚・不倫コラム全文はこちら -
更新日:2025年03月19日 公開日:2025年03月19日
 熟年離婚される夫の特徴とは? 離婚後の末路と回避する方法も解説 熟年離婚を回避するためには、まず「熟年離婚される夫の特徴」を知り、対策を検討していきましょう。ここでは、熟年離婚される夫の特徴や、離婚後の末路と回避法をご紹介します。 離婚・不倫コラム全文はこちら
熟年離婚される夫の特徴とは? 離婚後の末路と回避する方法も解説 熟年離婚を回避するためには、まず「熟年離婚される夫の特徴」を知り、対策を検討していきましょう。ここでは、熟年離婚される夫の特徴や、離婚後の末路と回避法をご紹介します。 離婚・不倫コラム全文はこちら -
更新日:2025年02月06日 公開日:2025年02月06日
 熟年不倫が許せない! 慰謝料請求や熟年離婚の流れを解説 40代50代などの夫婦においては、長年連れ添った配偶者が別の方と不倫しているケースがあります。このことを、「熟年不倫」と呼ぶことがあります。熟年不倫は、長い間信頼していた相手から裏切られる行為である... 離婚・不倫コラム全文はこちら
熟年不倫が許せない! 慰謝料請求や熟年離婚の流れを解説 40代50代などの夫婦においては、長年連れ添った配偶者が別の方と不倫しているケースがあります。このことを、「熟年不倫」と呼ぶことがあります。熟年不倫は、長い間信頼していた相手から裏切られる行為である... 離婚・不倫コラム全文はこちら

