親権を他方の親が有し、子どもと離れて暮らすことになる場合、子どもと面会するために、「面会交流」についての取り決めを行います。面会交流は離婚の際にもめることの多い問題です。
本ページでは、面会交流について取り決めをする際のポイントや話し合いがまとまらないときの対処法、拒否権、面会交流調停や審判などについて、弁護士が解説します。
目次 [非表示]
面会交流とは? いつ取り決めを行う?
面会交流とは、離婚後に子どもと離れて暮らすことになった親(非監護親)が、子どもに面会して一緒に時間を過ごしたり、文通などの交流をしたりすることです。
面会交流は、民法の条文上、親の権利として認められているものではありません。しかし、父母が協議離婚(夫婦間の話し合いによる離婚)をするときに、協議で定めるべき子どもの監護について必要な事項として、民法に明示されています(民法766条1項)。
親権の帰属は離婚時に決定する必要がありますが、面会交流を取り決める時期については、法律で規定されていません。離婚届には、面会交流の取り決めの有無について記載する箇所がありますが、なにも取り決めずに空欄で提出しても離婚をすることは可能です。
しかしながら離婚時に取り決めておかなければ、あとから面会交流についてトラブルが発生するおそれがあります。
なにより、子ども自身にとって、実親と面会交流を続けることにより適切な親子関係を築いていくことは、精神的な安定をもたらすと考えられていることから、空白の時間を作らないですむよう、離婚後すぐから面会交流ができるように合意しておきたいものです。
そのため、養育費や財産分与、慰謝料などとともに、面会交流についても離婚時に取り決めておいたほうがよいでしょう。
なお、離婚の前に父母の一方が子どもをつれて別居してしまい、子どもに会えていない場合には、離婚成立の前でも、相手方に対して子どもに会わせるよう求めるため、家庭裁判所に面会交流調停の申し立てをすることができます。
面会交流を行う条件の決め方
面会交流の回数や頻度などの条件は、まずは父母間での話し合いによって決めていきます。
話し合いで取り決める主な内容
- 面会交流の可否
- 面会交流の方法(対面、電話、メールなど)
- 面会交流の頻度
- 面会交流の時間
- 面会交流に関する連絡の手段
- 面会交流の待ち合わせ場所や実施場所
対面での面会交流を行うことの合意はできているけれど、面会交流の頻度や時間などの条件のみでもめている場合は、話し合いで合意できる可能性があります。
話し合いでまとまった場合は、口頭の約束だけでは合意内容について証拠が残らず、あとからトラブルになりやすいため、合意内容を離婚協議書や公正証書など書面にしておくことがおすすめです。
なお、面会交流の取り決めの際に、面会交流の実施と養育費の支払いがセットにされて交渉されることがありますが、面会交流と養育費は別個のものであり、切り分けて考える必要があります。
養育費が支払われなかったことは、面会交流をさせない理由にはなりません。逆に、面会交流ができないことは、養育費を支払わない理由になることもありません。
面会交流について話し合う上で、重要なことは「面会交流は子どもの権利である」という点です。離婚が高度に感情的な問題のため、親の気持ちを優先してしまいがちですが、面会交流を取り決めるにあたっては、子どもの親として、子どもの利益を最優先に考えましょう。
面会交流は拒否できる?
適切な面会交流が行われることは、両親の離婚(別居)を経験した子どもの利益にかなうものと考えられています。そのため、子どもと離れて暮らす親と子どもを会わせないようにすることは、原則として許されず、面会交流は実施されなければなりません。
面会交流は「子どものためのもの」です。だからこそ、面会交流の実施については、子どもの利益を1番に優先して考慮することが求められます(民法766条1項)。
もっとも、場合によっては、面会交流を行うことが子どもの利益にかなうものとは言えないこともあるでしょう。その場合は、面会交流が認められない、もしくは一定の制限を付ける必要があると判断されることもあります。
両親の離婚や別居は、子どもにとって、とても大きな出来事です。
子どもがこの出来事を乗り越えて健やかに成長していくために、別居や離婚後も面会交流を円滑に行っていくことは、両親の離婚や別居を経験した子どもにとって、とてもよい影響を与えます。
子どもは、面会交流を通して、どちらの親からも愛され、大切にされていることを実感し、安心感や自信を得ることができるのです。この安心感や自信は、子どもが生きていく上で大きな力となりますし、両親の離婚(別居)という現実を受け入れる支えにもなります。
以下の特設ページでは、面会交流の解決事例や弁護士相談のメリットなどを解説しています。ぜひご参考ください。
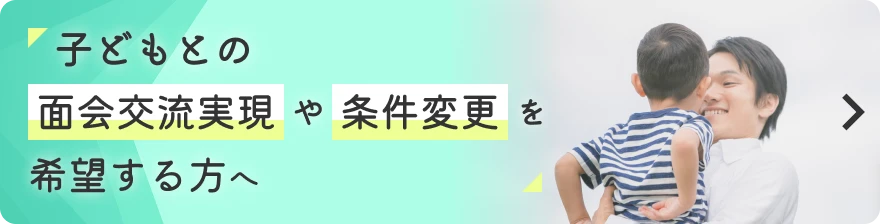
子どもとの面会交流が認められないケース
子どもが「会いたくない」と言う場合
面会交流は、子どもにとっての利益を優先した上で決定されるものです。したがって、子ども本人が本心から「会いたくない」と言っている場合は、子どもの意思を尊重し、面会交流が認められないことがあります。
ただし、子どもの「会いたくない」という言葉は、一緒に暮らす親からの愛情を守りたいがゆえの発言ということも考えられるでしょう。
家庭裁判所の実務では、10歳前後を目安に直接に意思の確認をし、意思を重視する傾向にあります。ただし、同居親に遠慮するなど、意思が親の意向による影響を受けることがあるため、その気持ちは本心なのか、子どもの意思表示の評価は慎重になされます。
また、子どもが「会いたくない」と言っている場合も、その他の事情から、面会交流を実施することが子どもの利益にかなうと判断される場合には、面会交流を認める審判がなされることもあります。
子どもの生活に悪影響を及ぼす場合
両親の離婚によって、子どもの精神が不安定になってしまうことがあります。
たとえば、面会交流を行ったあと、暴力を振るうようになったり、学校に行けなくなったりするなど、子どもの精神がさらに不安定になる場合は、面会交流が認められない可能性があります。
非監護親による不当な干渉等がみられる場合
非監護親(子どもと別に暮らす親)が、監護親(子どもと共に暮らす親)に対して干渉をする、暴言を吐く、激しく非難するなどの行為がある場合、面会交流の内容を決定する際にその事情が考慮されます。
非監護親に薬物使用の疑いやアルコール依存等がある場合
非監護親が、薬物使用やアルコール依存等によって正常に物事を判断できず、子どもの生命に危険があると判断される場合は、面会交流が認められない可能性が高くなります。
非監護親が子どもを連れ去るリスクがある場合
非監護親が子どもを連れ去ろうとするリスクがあると判断された場合、面会交流が難しくなる傾向があります。特に、過去に子どもを連れ去ろうとした、もしくは連れ去ったことがあると、面会交流が認められない可能性が高まります。
非監護親が監護親や子どもに暴力を振るう場合
婚姻中、非監護親が監護親や子どもに対して暴力を振るっていた、暴言を吐き続けていたなど、DVがあったケースがあります。この場合、子どもの身体に危害が与えられるリスクが高いと考えられるため、面会交流が認められない可能性が高いでしょう。
話し合いがまとまらないときの対処法
面会交流についての話し合いがどうしてもまとまらず、どうしたらよいのかと悩むケースも少なくありません。そんなときは、家庭裁判所に面会交流の調停で調停委員を介して話し合いをして決めるか、または審判を申し立てて裁判所に決めてもらうことができます。
申立先は、調停の場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、審判の場合には、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所となりますが、どちらも当事者が担当する家庭裁判所について合意できれば、その裁判所で行うことが可能です。
裁判所を利用した話し合いとはいえ、相手方に対して一人で面会交流の取り決めをしていくことは負担が大きなものです。不安がある際には、弁護士に相談するようにしましょう。
ベリーベスト法律事務所では、安心してご相談いただけるように、離婚専門チームの知見ある弁護士が親身になって対応いたします。離婚に関するお悩みがあるときは、お気軽にお問い合わせください。
お悩みの方はご相談ください
面会交流について争う調停・審判とは
面会交流の調停・審判
面会交流が話し合いで合意できなかった場合は、まずは家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停を通じても話がまとまらなかったときは、審判へ移行します。審判ではこれまでの話し合いの内容などから、どのようにすべきか判断を下されることになります。
調停や審判が行われる際、調停委員や裁判官が面会交流の可否や方法、回数等を判断するため、また、当事者が判断の参考にするため、家庭裁判所調査官による調査や試行的面会交流が実施されることがあります。
子どもが15歳以上の場合は、その子どもの意見を聞かなければなりません。家庭裁判所の実務では、子どもが10歳前後から、子どもの意見を聞いています。
家庭裁判所調査官による調査
家庭裁判所で開かれる親権に関する調停や審判では、裁判官、調停委員だけでなく家庭裁判所調査官がその判断に大きな影響を与えます。
家庭裁判所調査官は、心理学、社会学、教育学、社会福祉学等の人間関係諸科学の専門知識を有する裁判所職員(国家公務員)です。子どもの意思や面会交流が親子に与える影響について、調査を実施します。
調停委員や裁判官は、家庭裁判所調査官による調査の結果を重視するため、この調査は非常に重要です。
試行的面会交流
試行的面会交流とは、子どもと非監護親が裁判所で面会するものです。非監護親が面会でどのように子どもと接するか、子どもの非監護親に対する気持ち、面会交流についての意思を観察、調査することを目的として行われます。
家庭裁判所調査官が立ち会って、裁判所内の観察室と呼ばれる部屋での交流の様子を観察します。試行的面会交流では、監護親が、非監護親と子どもが交流する様子を観察することも可能です。観察室の様子は外からは見えますが、中からは見えないようになっています。
試行的面会交流がうまくいけば、調停委員の面会交流に関する印象もよくなります。一方で試行的面会交流の際に、子どもと親が上手にコミュニケーションをとれず、ぎくしゃくした様子だったり、子どもが一方的に激しく拒否をしたりといった場合は、面会交流をすべきではないと判断されるおそれもあります。
面会交流に関するよくある質問
親権がなければ、子どもに会うことはできませんか?
親権がない非監護親でも、親子関係は消滅することなく、子どもと一緒に時間を過ごす権利(=面会交流権)が認められています。
ただし、面会交流権があるとはいえ「子の福祉または子の利益」が最優先です。...
離婚調停が成立した後も子どもに会うためには、どのような合意をする必要がありますか?
調停で離婚する場合、調停調書という合意書を作成します。この調停調書に、子どもとの親子交流(面会交流)についての取り決めを盛り込むことが必要です。調停調書に親子交流(面会交流)の定めを明記しておかない...
続きを読む離婚後、親権をとる配偶者が「義父母(子どもにとっての祖父母)には子どもを会わせない」と言っているとき、祖父母は子どもに会えませんか?
面会交流権は、子どもが親に会う権利あるいは親が子どもに会う権利と考えられますので、祖父母に面会交流権があるというのは難しいと考えられます。
そこで、調停において、親が子どもと親子交流(面会交流...
お悩みの方はご相談ください

